「女性の社会進出」という言葉は、もう聞き飽きた。
企業の広報誌にも、政治家のスピーチにも、研修資料にも、必ずと言っていいほど登場する。
でも、その反対側——「男性の家庭進出」なんて言葉は、ほとんど聞かない。
もはや幻のポケモンか何か?ってくらいレアだ。
女性が社会に出るとき、家庭での役割は減らない。
朝ごはんを用意して、子どもを送り出し、仕事をして、帰宅後は夕飯の支度と片付け。
社会進出って、要するに家庭業務にフルタイムの仕事をトッピングすることだ。
二郎系ラーメンの「全部マシ」みたいなもんで、満腹を通り越してもう笑うしかない。
一方、男性が家庭に入ると、それは“手伝い”として特別扱いされる。
休日に一度カレーを作れば「料理上手」、保育園に送れば「イクメン」。
女性がやると評価ゼロなのに、男性がやるとスタンディングオベーション。
これ、採点基準どうなってる?
男性の家庭進出は、多くの場合“イベント化”している。
参観日や運動会、キャンプ、誕生日ケーキ作り。
外から見えて、SNSにも載せやすい仕事は喜んで引き受けるけど、
毎日繰り返される皿洗いや洗濯物畳みは、なぜかミッションから外れている。
でも、家事や育児は「やった瞬間」だけが仕事じゃない。
全体を把握し、先を読んで、段取りを組み、必要な準備を整える。
この「全体を担う」という感覚を、男性が引き受けることはまだ少ない。
そう、家事って将棋みたいなもんで、常に先手を打たないと詰むのだ。
本当の家庭進出は、“手伝う”から“担う”に変わることだ。
食洗機の使い方を覚えるだけじゃなく、食器が汚れる前の流れを考える。
洗濯機を回すだけじゃなく、天気や家族の予定を踏まえて干すタイミングを決める。
送り迎えをするだけじゃなく、習い事のスケジュールや持ち物リストまで把握する。
このレベルになると、家庭のCOO(最高執行責任者)だ。
でも、それをやるには、社会全体の台本を変えなければならない。
「男は稼ぎ手、女は家庭」という旧型モデルを捨て、制度も文化も変えていく必要がある。
男性の長時間労働を前提にした職場、育休を取ると出世が遠のく空気——
これらがある限り、家庭進出を望む男性も孤立する。
女性の社会進出は、半分の物語にすぎない。
もう半分は、男性の家庭進出だ。
それが当たり前になったとき、初めて“平等”という話題を話すことができる。
その日はいつ来るのか。
少なくとも、「手伝った感」に拍手しているうちは、まだまだ遠い。
…そして私は今日も、更年期というスパイスが加わったうえに、二郎系の「全部マシ」生活を続けている。



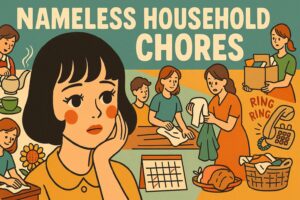







コメント